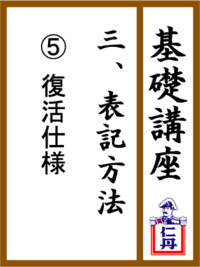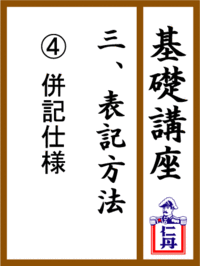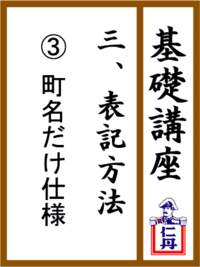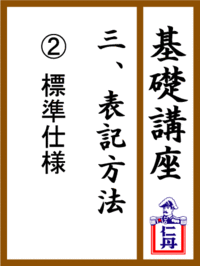2011年08月09日
仁丹町名表示板 伏見仕様
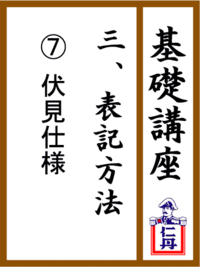
いささか番外編かもしれませんが、「伏見仕様」としました。
現在の伏見区のことですが、行政区名の欄が『伏見市』と右横書きとなっています。
伏見市が存在したのは昭和4年5月1日~昭和6年3月31日のわずか1年と11ヶ月。
ということは、町名表示板もこの期間に設置されたことになります。
基礎講座 二.実例 ⑤伏見市の場合 と内容が重複しますが、とにかく非常に興味深いところは、表示板の長さが短いだけでデザインは京都市の「町名だけ仕様」と同じだということです。
だから、「伏見仕様」として仲間に入れてみました。
京都市の町名だけ仕様 伏見仕様

なぜ、京都市と同様のデザインとなったのか?
これ以上は、推理の世界になりますので、ここでは割愛します。
みなさんのお考えをコメントとして寄せていただければ嬉しく思います。
書式は次のとおりです。
【伏見仕様】 伏見市 + 町名 + 商標
表示板の大きさは、縦が京都市の約2/3の60cm、横が京都市よりも3cm程度小さい12cmで、実は奈良市と同じ大きさのようです。
ただ、奈良のように商品ロゴはありませんので、シンプルで美しい仕上がりとなっています。
Posted by 京都仁丹樂會 at 06:00│Comments(1)
│表記方法
この記事へのコメント
>なぜ、京都市と同様のデザインとなったのか?
>これ以上は、推理の世界になりますので、ここでは割愛します。
>みなさんのお考えをコメントとして寄せていただければ嬉しく思います。
『伏見の現代と未来』 (聖母女学院短期大学伏見学研究会編 清文堂)
『京都の江戸時代をあるく』 (中村武生 文理閣)
などによりますと、京都市と紀伊郡伏見町との合併話しは明治30年代からあったようです。
ただし、伏見町としては”吸収”ではなくあく
までも”対等合併”を強く希望していたと。
そのために、伏見町としてのアイデンティティの確立を急いでいたようです。
寺田屋再建もその政治的流れと関連していると中村武生先生は見ておられます。
そして、紆余曲折を得ながらも、昭和4年にめでたく伏見市へと昇格しました。
ということで、ここからは私の完全な推理なのですが。
京都市への合併が見込まれていた伏見市に対して、森下仁丹が積極的に町名表示板の設置を働きかけるでしょうか?
もしかしたら、逆に伏見市側がアイデンティティのさらなる向上のために、積極的に動いたのではないのでしょうか?
そこで、遅かれ早かれ京都市に合併されるのならと、京都市と同じデザインの表示板を採用したのではないのでしょうか?
>これ以上は、推理の世界になりますので、ここでは割愛します。
>みなさんのお考えをコメントとして寄せていただければ嬉しく思います。
『伏見の現代と未来』 (聖母女学院短期大学伏見学研究会編 清文堂)
『京都の江戸時代をあるく』 (中村武生 文理閣)
などによりますと、京都市と紀伊郡伏見町との合併話しは明治30年代からあったようです。
ただし、伏見町としては”吸収”ではなくあく
までも”対等合併”を強く希望していたと。
そのために、伏見町としてのアイデンティティの確立を急いでいたようです。
寺田屋再建もその政治的流れと関連していると中村武生先生は見ておられます。
そして、紆余曲折を得ながらも、昭和4年にめでたく伏見市へと昇格しました。
ということで、ここからは私の完全な推理なのですが。
京都市への合併が見込まれていた伏見市に対して、森下仁丹が積極的に町名表示板の設置を働きかけるでしょうか?
もしかしたら、逆に伏見市側がアイデンティティのさらなる向上のために、積極的に動いたのではないのでしょうか?
そこで、遅かれ早かれ京都市に合併されるのならと、京都市と同じデザインの表示板を採用したのではないのでしょうか?
Posted by shimo-chan at 2011年09月04日 20:28